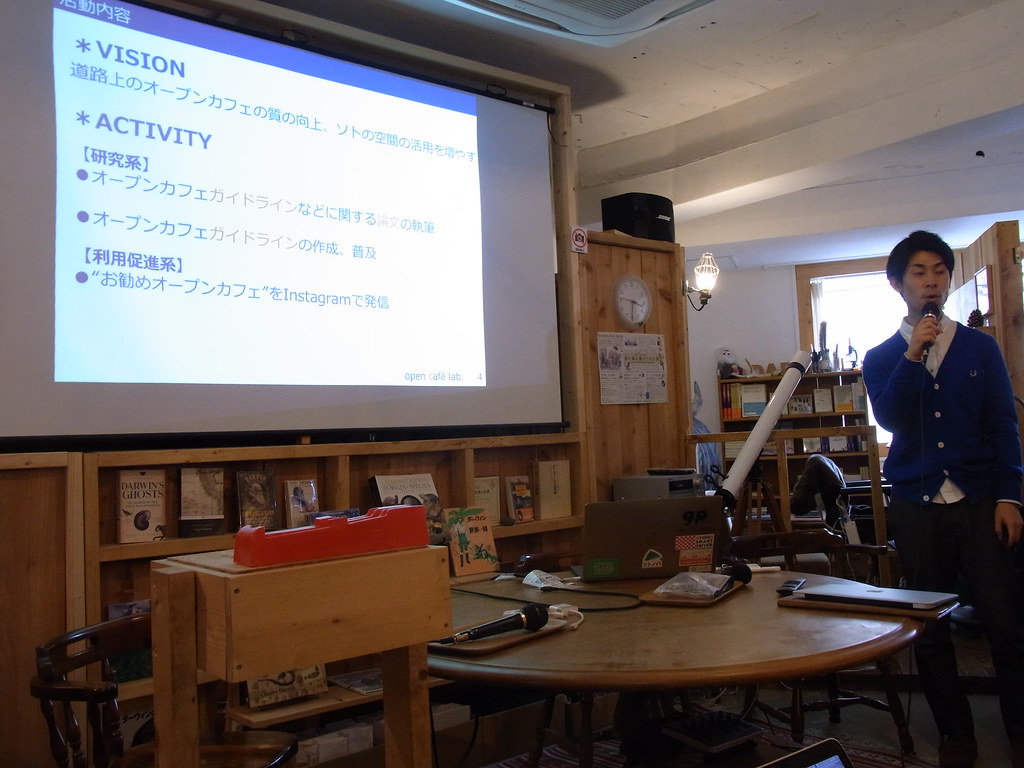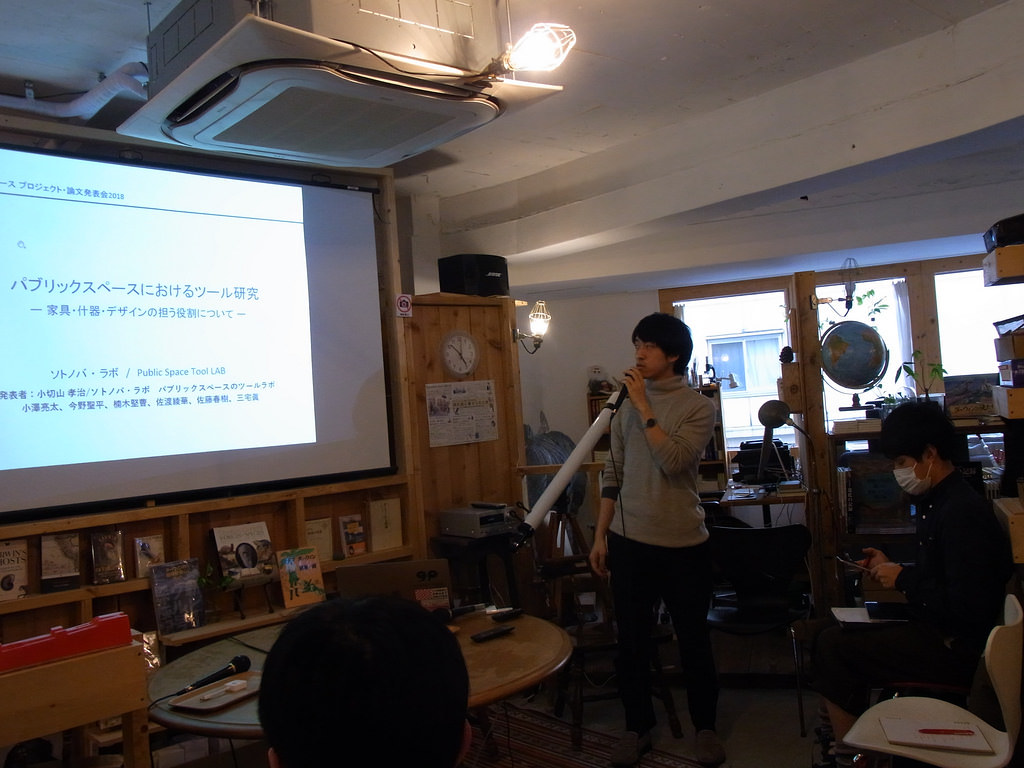ラボの成果も大公開!ソトの現場とリサーチをつなぐ「パブリックスペースプロジェクト・論文発表会2017」ソトノバTABLE#26レポート

2018年3月5日のソトノバ TABLE#26では、3年目を迎えた「パブリックスペースプロジェクト・論文発表会」を開催しました!
今年は3つのプロジェクト・事例視察報告のほか、ソトノバ・ラボに所属する6つのラボも1年の活動成果を発表しました。「ソトの最新海外事例」、「ソトを概念から考える」、「ソトを仕組みから考える」、「ソトをデザインとリサーチから考える」の4つのセッションで進行し、発表者どうしでのクロストーク、会場も交えて議論を進めました。
梗概はissuuでも公開していますよ!
オーストラリア・ソトの最前線
発表会は最新海外事例紹介からスタート!視察から帰ってきたばかりのソトノバ・泉山編集長が、オーストラリア・シドニーとメルボルンのフレッシュな情報をシェアしました。
Tactical Urbanism 4ガイドが発行されているのが、ここオーストラリアとニュージーランドです。ガイドの編集を行ったCoDesign StudioやASPECT STUDIOSと意見交換のために訪れた泉山さんは、「シドニーのソトは、日本とは市民の振る舞い自体が違っている。大人も本気で、身体を動かし、遊べるようなデザインになっているのが特徴」だと語ります。そのせいか、街なかにはフィットネスクラブはないということでした。
また、Livableな都市ナンバー1に選出されたメルボルンのストリートについてもレポートしました。都心では「シティベンチ」としてデザインされた座り場の整備に力が入れられています。郊外でもショッピングセンター前が、人工芝と地元の人々の手でつくりこんだファニチャーによる居場所が展開されていたそうです。
オーストラリアのパブリックスペースに対する取組みは、市民からのアクションはそれほど盛んでなく、行政主導の社会実験が多い日本と共通する点があることもわかったそうです。規制は厳しいけれど、1階の建物用途はお店になっており、目の前のパブリックスペースにコミットする意識が高い。そうした思いを形にする・育むタクティカルな実践の様子が発表から伝わりました。
概念から、パブリックスペースを変える!
次のセッション【ソトを概念から考える】は、ソトノバ・ラボの2つのワーキンググループからの話題提供でした。どちらも、パブリックスペースを変えていくための、概念を普及するガイドラインづくりを目指しています。
まずは、タクティカル・アーバニズム・ラボよりメンバーのソトノバ副編集長・荒井さんが「4か国の比較からみる日本におけるタクティカル・アーバニズムの概念導入の意義と有効性」と題して発表しました。このラボは、アメリカから世界に波及してきたタクティカル・アーバニズムの活動に共感して活動を始めました。タクティカル・アーバニズム公式ガイドを作成し、国内での前例をしっかりまとめることで、タクティシャン=アクション実践者のための環境が整い、行政に対するメッセージにもなると考えています。
先行してTUガイドを出している北米・ラテンアメリカ・イタリア・オーストラリア&ニュージーランドの4か国について、タクティカル・アーバニズムが取り入れられた背景と特徴についてまとめた結果が紹介されました。北米では住民が自ら動いて、パーキングデーのようなアクションが生まれ、行政によるパークレット制度づくりへと一連の流れでつながっています。しかし例えば、南米やイタリアでは、地域の中での不平等をゲリラ的に行政に訴える方法として取り入れられており、同じタクティカル・アーバニズムでも概念に幅があることが示されました。
これら各国の特徴を踏まえTUラボでは日本のタクティカル・アーバニズムの特徴を①アクティビスト発意のゲリラ的アクション型、②エリアマネジメント組織等による利活用実験型、③行政主導の社会実験型の3つのタイプがあると整理。エリアマネジメント型・行政主導型は、ハード整備に向けてその地域にマッチするか確かめる術である一方、アクション型はまちの中の人々をつなぐアイデアを提示するもので、他の地域へも波及するとその可能性を語りました。
続く、プレイスマネジメント・ラボの活動報告は、メンバーのソトノバ副編集長・三谷さんより発表がありました。
「場(プレイス)」の管理の質の向上に問題意識を持つラボメンバーが生み出した「プレイスマネジメント」という概念、取り組んだのは、まずこの言葉の定義からだったそうです。三谷さんは「どうしても維持管理の効率化に目が向いてしまう管理者に、活動を生み出す・愛される場をつくる方向に目を向けて欲しい」と訴えます。
ラボでは現在、管理者が自身の役割に気づいたり、これまでの取り組みを省みるセルフチェック方式のガイドラインについて作成を進めています。TUのような動きが市民から出てきている中、ガイドラインを普及することで、パブリックスペースの管理者がそれらを受け入れる素地作り、想像力を養うことになるとのことでした。
クロストークでは、「発意」すること自体に価値を置く地方都市でのTUのあり方や、第3者も診断できる形でのプレイスマネジメントのガイドライン化の可能性について語り合いました。
道路空間の可能性を語ろう!
【ソトを仕組みから考える】のセッションでは3つの発表があり、主に道路空間に居場所をつくるデザインと仕組みについて、ディスカッションしました。
1番手はオープンカフェ・ラボから森さんが、「日本版オープンカフェガイドラインを通じた、デザインとマネジメント手法の提案」について発表しました。
ラボでは、各地のオープンカフェ運営者へのアンケート結果を交えて、特に断面レイアウトの類型、類型別に見た運営上のメリット・デメリットを研究しています。また、別途インスタグラムで発信してきたデータを「アイテム」として、カフェ事業者が参照できる指針をつくっています。
森さんは「道路占用については制度緩和が進む中、許認可のハードルを越えるよりも、運営の持続性が課題」と話します。会場から、エリマネの実態に詳しい泉山編集長も議論に加わり、街のオープンカフェの運営を、エリマネ団体が一手に引き受けることは負担も多く、海外のように個々の飲食店が営業の延長で出せるようにしていくことが自然な状況ではないかと問題提起しました。
続いて、今夏話題になった「おおみやストリートテラス- 道路予定区域利活用社会実験 –」について、アーバンデザインセンター大宮(以下、UDCO)の新津さん、石黒さんからプレゼンです。
日常的な「都市街路文化」の創出を目指したという、道路予定区域の利活用プロジェクト「おおみやストリートテラス」。
この30年間、ロングタームでの街の動かし方を課題としてきたJR大宮駅の東側エリアは、開発の過程で現れる既存施設跡地や公共用地活用をつなぐ連鎖型まちづくりを目指す方針を決めました。そんな状況の中で道路整備を控え、10年間ずっと工事中で、まちなみが崩れるのはもったいないと、今回のプロジェクトが始まったそうで、他の都市と比べると滞在できる屋外空間が少ないという大宮のソトの課題にもアプローチできるように留意したとのことでした。
厳密には道路ではないために、原状回復や警察の道路使用許可不要!!ペイントだってできてしまいます。そして、「今、そこにあるもの」を活かすということでH鋼カウンター、「将来、そこにあるもの」をイメージしてサイクルラックカウンターが設置されたことなど、歩道に置くファニチャーへのこだわりについても語っていただきました。
このセッション最後は、そんな大宮で今年パーキングデーの実践も行った、パークレット・ラボの石田さんから「国内外におけるパークレット事例の評価総覧」について成果発表がありました。
ラボでは、各都市のパークレットマニュアルの翻訳から特徴を比較。サンフランシスコ市の「Parklet」が駐車帯に設置されるのに対し、都市によって条件が違う場合は「Street Seats」と呼ばれるなど名称が異なることが明らかになりました。これをふまえ、ラボでは日本でのパークレットの名称やデザイン等の質の保証制度を検討しています。
3者の発表に対して、会場から「道路空間の現場ではプレイヤーが動きにくい状況がわかった。その声を伝えていく仕組みがあると良い。」との意見をもらい、石田さんは、パークレット・ラボが関わった「ストリートウィーク」を挙げ、今後も道路を考えるキャンペーンを主催し、その役割をソトノバが担っていきたいと答えていました。
また、クロストークでは「ファーニチャーが集積している方が魅力的だ」、「1つ1つが大きいとコミュニケーションしにくい場合もある」など、デザイン談義も盛り上がりました。パークレットの大きさ(2.5×5m)はそうした観点から考えるとちょうど良いそうです。
ソトのリサーチのこれから
最後のセッション【ソトをデザインとリサーチから考える】は、リサーチのあり方自体がテーマでした。
はじめに、慶應義塾大学の現役学生、荒木さん、新井さんが、熊本復興の過程に入りこみ「アクションリサーチ」した成果の「セルフビルド仮設建築を用いたまちづくりへの戦術的介入」について紹介しました。地震後、多くのビルが解体されてできた空地をイベントスペースとして活用していった「熊本まちのたねプロジェクト」としても知られています。
クラウドファンディングを用いて、このプロジェクトを草の根から立ち上げたお2人。復興の過程では、自分の手で何かやりたい人の動きがソフト寄りだという印象を持ち、行政側の経済・都市計画といった大きな復興活動(マクロ)と、民間・市民の小さな活動(ミクロ)が乖離しているような印象を抱いたといいます。
そこで、私的かつハードに対する支援手法の開発の必要性を強く感じたそうです。はじめたのは、個人レベルで平時にストックできるセルフビルド型の避難所づくりでした。もともと住宅地や郊外での活用を想定していたそうですが、まちの人からはむしろ商店ブースのように使いたいという声が上がり、既存のイベントから利用してもらうことに。その後、住民主体の使いこなしの変遷についても、データとして蓄積し、地域に研究を還元しています。
続く、パブリックスペース・ツール・ラボの小切山さんは、「パブリックスペースにおけるツール研究-家具・什器・デザインの担う役割について-」と題して発表しました。
ラボの大きなゴールは、パブリックスペース活用に有効なツールの製作です。そこに向けて、「事例」、「つくりかた」、「使い手」、「場」、「時系列」の研究群に取り組んでいます。場の制約に配慮したツールの原理がわかりやすくまとめられていました。
最後はアクティビティデザイン・リサーチ・ラボからメンバーの一人である筆者より「パブリックライフ研究レビューと調査実践報告」と題してプレゼンをしました。
この1年間、ソトノバはヤン・ゲールのPublic Life Studiesに学びつつ、オリジナルフォーマットを作成し、各地でアクティビティ調査を実践してきました。ラボでは、こうしたフォーマットの無料公開にふみきっているゲールらの意図を読み解くために、ソトノバフォーマットとの詳細比較を行いました。
その結果、日本の社会実験では「正確な実態データ」が求められますが、ゲールは地域ステークホルダーが「傾向データ」を共有できることを重視しているという、アクティビティ調査実務自体の狙いの違いが浮き彫りなりました。
ゲールらが近年提唱する「Action Oriented Planning」という日常のアクティビティ調査(Measure)—実験(Test)—日常と実験時の比較による改善提案(Refine)という計画サイクルが鍵を握っているとみて、ラボでは、次の1年間、日本の社会実験の枠組み自体にも問題提起していこうと思います。
クロストークでは、会場の質問を受けつつ、開発者の権利に配慮しながら、まちに貢献するためにツールやリサーチ方法の「オープンソース」化をどこまで進めるまで、意見を交わしました。
ソトを動かすプレイヤーの視点
今年の発表会では、ソトを動かすプレイヤーの多様性が浮き彫りになりました。
全てのプレイヤーが共通して視点としてもっておくべきレイアウトや制度、そして、プレイヤーの個性を活かすマネジメントの議論が、会全体を通してできたのではないでしょうか。
クロージングの後、続く懇親会でも、ソトをテーマに話に花が咲きました。
今回の発表会も、パブリックスペースのホットな話題が飛び交いました。
来年度も開催し、ソトをじっくり考えるコミュニティの輪を広げていきたいです!
パブリックスペースプロジェクト・論文発表会ソトノバTABLE#26概要
| 日時 | 2018年3月10日(土)14時~20時 |
| 会場 | 好奇心の森「ダーウィンルーム DARWIN ROOM」 東京都世田谷区代沢5-31-8 |
| 主催 | ソトノバ |
プログラム
| ソトノバ・イン | |
| ソトノバ・イントロ | |
| 【ソトの最新海外事例ーオーストラリア編】 | |
| 「シドニー・メルボルン視察報告」 泉山塁威(東京大学助教/ソトノバ編集長)、山崎嵩拓、原万琳(ソトノバ・ラボ) |
|
| 【ソトを概念から考える】 | |
| 「4か国の比較からみる日本におけるタクティカル・アーバニズムの概念導入の意義と有効性」 荒井詩穂那、泉山塁威、山崎嵩拓、原万琳、小泉瑛一、西田司、矢野拓、大西春樹、豊間友佳子(タクティカルアーバニズム・ラボ) |
|
| 「プレイスマネジメントについて」 三谷繭子、遠藤友里恵、角間裕、佐渡綾華、高橋凛、日置大輔、三谷繭子、森悠太郎、矢野 拓洋(プレイス・マネジメント・ラボ) |
|
| 発表者クロストーク・質疑回答 | |
| 【ソトを仕組みから考える】 | |
| 「日本版オープンカフェガイドラインを通じた、デザインとマネジメント手法の提案」 佐藤春樹、泉山塁威、木村陽一、森悠太郎(オープンカフェ・ラボ) |
|
| 発表者クロストーク・質疑回答 | |
| 【ソトを道路空間から考える】 | |
| 「おおみやストリートテラス- 道路予定区域利活用社会実験 -」 新津瞬、石黒卓(アーバンデザインセンター大宮) |
|
| 「国内外におけるパークレット事例の評価総覧」 石田祐也、荒井詩穂那、泉山塁威、氏川拓郎、桑迫修平、中埜智親、三浦詩乃 (パークレット・ラボ) |
|
| 発表者クロストーク・質疑回答 | |
| 【ソトをデザインとリサーチから考える】 | |
| 「パブリックスペースにおけるツール研究-家具・什器・デザインの担う役割について-」 小切山孝治、小澤亮太、今野聖平、楠木堅曹、佐藤春樹、佐渡綾華、三宅眞(パブリックスペース・ツール・ラボ) |
|
| 「パブリックライフ研究レビューと調査実践報告」 三浦詩乃、泉山塁威、三浦魁斗、三谷繭子、山田広明(アクティビティデザイン・リサーチラボ) |
|
| 発表者クロストーク・質疑回答 | |
| 総括 | |
| ソトノバ・ドリンクス/グループフォト | |
| クロージング | |