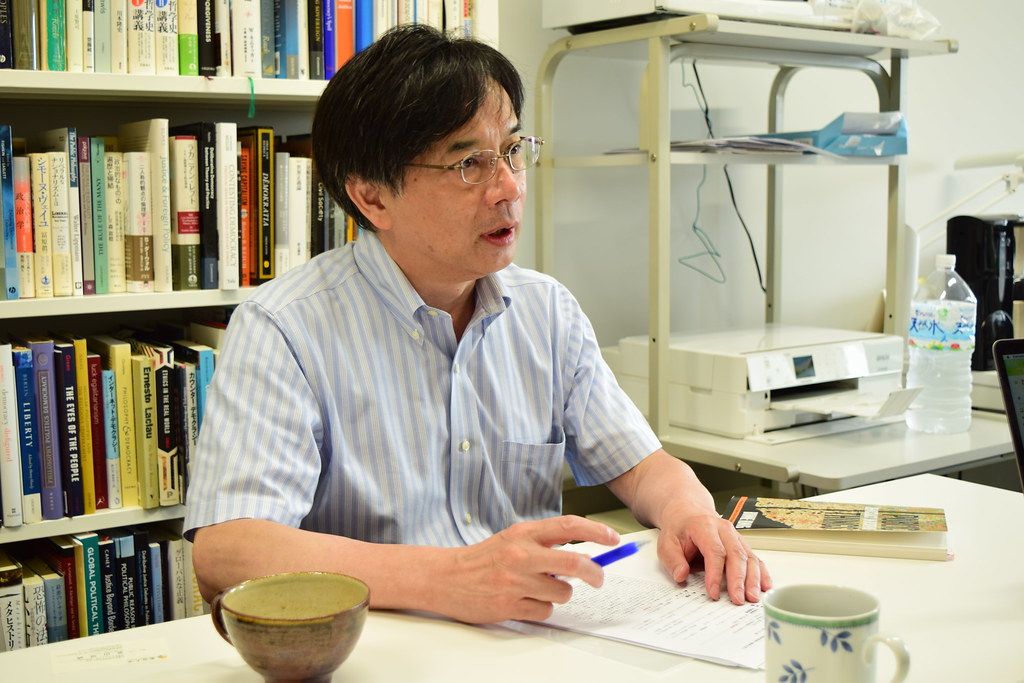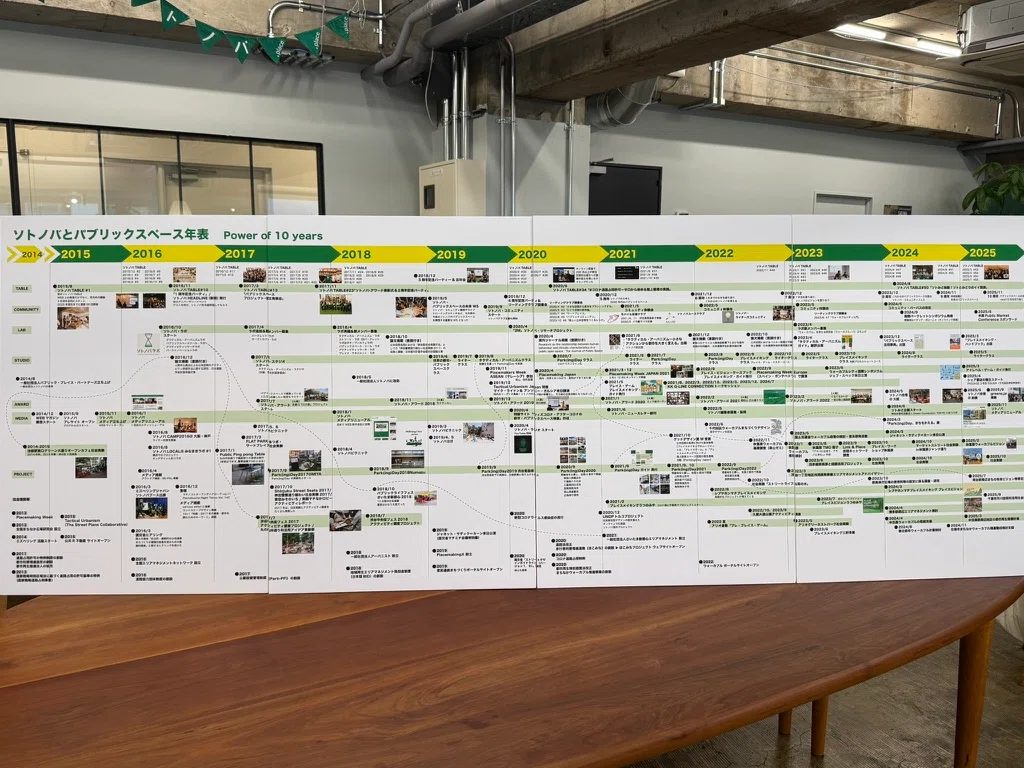いま、2018年の公共性について考える【齋藤純一インタビュー:前編】
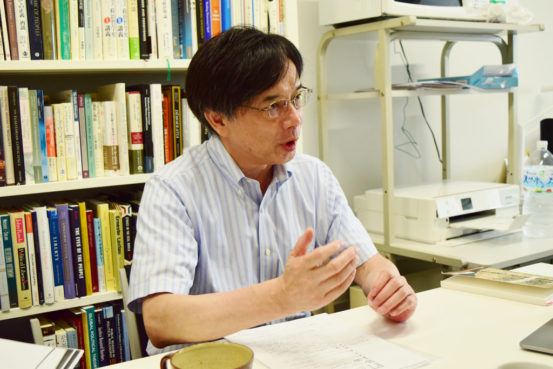
ソトノバを考えるときに必ず登場する「パブリックスペース」という言葉。そのパブリック、公共性とは、何を指すのか?という疑問に答えてくれたのが、齋藤純一先生が執筆された『公共性』です。2000年に出版されたこの本で、齋藤先生は公共性をOfficial, Open, Commonという3点から定義し、公共性に対する深い思考を展開されています。政治学の分野を超え、都市デザインの分野の人々にとっても、公共性を考える際の「必読書」となっています。
出版から18年経ったいま、齋藤先生は公共性に関しどんなことを考えておられるのでしょうか。また、近年のパブリックスペースの活用については、どのような意見をお持ちなのでしょうか。ソトノバ編集長・泉山が、齋藤先生にインタビューします!
自治体の予算減による、パブリックスペースの変化
泉山:
都市計画や都市デザインの分野ではパブリックスペースの利活用に大きな関心が寄せられ、国でも規制緩和などの制度を作り、それを支援する動きがあります。そのような中で、齋藤先生は、パブリックスペースの状況に関して、どのようなことをお考えでしょうか。
齋藤先生:
まず一つは、自治体の予算減を背景にした、空間の変化です。ナイキが関わった宮下公園の事例のように、公園は公園だけど、命名権を売ろうとして、実際は限られた人にアクセスを閉じていくということがあります。アメリカ・サンフランシスコの公園でも、1時間何十ドルのように、時間貸しにするという動きがありました。最終的には実現しなかったようですが。要するに、自治体もお金がなくなってきているので、なんとか収益をあげようと公園を有料で貸していこうとするわけです。これは、多様な人がその場に同時にいる機会を喪失させます。利用者が細切れになって、それぞれのサークルごとの遊びに閉じていってしまう。自治体の予算の減少により、公園をできるだけ効率的に活用しようとする思考が生まれ、命名権の売買や有料での時間貸しにつながっていきます。そうするとやはり閉じていくわけですよね。よく言われることですけど、同時にいろんなアクセスがあるという関係が作りにくい。結局、私的な利用になっていくところがあるのではないかという感じがします。
齋藤先生:
もう一つは、公園の管理運営を地元の人に委ねるということが起きています。これは行政にとってありがたいことですから、そのパフォーマンスが良ければ、一定程度の助成を続けたりもしています。このような、一歩後ろに引いたGovernment of Government、 直接行政主体が統治するのではなく、住民に運営管理を委ねて、それを背後から評価するというシステムが生まれてきている。これもやはり自治体にお金がないことが理由の一つでしょう。ただ、これは両義的です。一方では、自治と実験に開かれるという面があります。すなわち、誰がどのように使っているかなど具体的な情報がある人が、その使い方について考えてアイディアを生み出すなど、実験に開かれるということです。しかし他方で、行政によるコントロールは生き続けています。行政は評価権を手放さないわけですから、初期に比べてパフォーマンスを上げているかどうか、セキュリティの観点で一定の枠組みから出ていないかどうかをチェックします。そうすると一方では自治や自発性に委ねながらも、やはり他方ではある方向に向かって評価していく。この場合の評価軸は、多元的ではないかもしれませんね。私は現在のパブリックスペースの状況を見て、このような問題があるのかなと思っています。
泉山:
そうですね。確かに、日本も今そういう方向になってきていますね。
時間的「あいだ」と公共性
泉山:
齋藤先生が『公共性』を書かれてから18年が経ちました。いま先生がお考えになる「公共性」は、当時と変わらず普遍的なものなのか、あるいは何か変化があったのか、その点をお伺いしたいです。
齋藤先生:
それに関しては、3点の気づきがありました。
一つは、「公共性」を考えるうえでの、時間軸の存在です。『公共性』では、時間の「あいだ」、すなわち現在と将来の関係、現在と過去との関係をあまり強調していませんでした。例えば、放射性廃棄物や多額の財政赤字は、将来の市民にも関係のある問題です。この将来との関係という時間の「あいだ」も、「公共性」に関わるものなのです。あとは過去との関係もありますよね。例えば、憲法というのはひとつの時間的な成果、歴史的な成果です。ゆえに、批判しながらも維持していくこと、そういう過去のものを保持して付け加えていくことが必要なのではないかと思います。いずれにしても現在を中心とし、我々だけの意思で世界の在り方、公共的なもののあり方を決めないということは触れるべきだったかなと思っています。
経済的な格差が、空間的に翻訳されていく
齋藤先生:
二つ目は、格差の拡大についてです。2001年に『思想』で「社会の分断とセキュリティの再編」というものを書きましたが、その後予想したように、いや予想以上に格差が広がっています。そして、経済的な格差は空間的に翻訳され、具体化されていく。まだそれほどでもないのかもしれませんが、 ゲーテッドコミュニティ(Gated community)やセグリゲーション(Segregation)などに示されるように、人々が分断され交わらなくなっていく。同じ町に住んでいてもすれ違うことすらないような分断が、アメリカでは顕著になってきています。アメリカの政治学者が、全米8都市で行った調査があります。そこで分かったのは、昔は交わっていたような人々が、現在ではほとんど出会う機会がないということです。距離的にはそこまで離れていなくてもです。上位層は子どもを良い学校に入れるなど再生産に入る一方で、他方の下位層はアメリカンドリームが完全神話化しています。二世代前とは、まるで違う状態です。これはアメリカの話ですが、日本でもこのような分断が顕在化してきています。教育投資がその一例でしょう。
そういう自分とは違った場所(階層)に生きている人への関心が薄れてくると、公共的な関心がなくなってきます。すなわち、自分と異なる人々との間を媒介する関係がなくなってきているということです。そうすると、それぞれの階層ごとの政治的な選好が政治過程に反映されていくわけですが、他よりも影響力の強い富裕層にとって有利な法律や政策がより多く作られていきます。アメリカの研究では、実際の法律が富裕層/貧困層のどちらの利益や関心事を反映しているのかが調査され、やはり富裕層に偏っていることがわかりました。
格差全般が悪いわけではなく、不平等があったとしても正当化できる不平等であったらいいのですが、そういうことがおよそないままに格差が拡大しています。ジョン・ロールズも厳密な平等を唱えたわけではなく、不平等が全体の利益になるなどの条件があれば正当化できると議論しています。不平等は、最も不利な人に対して正当化できなければいけない。しかし、現状はそうではありません。格差の拡大をもう少し真剣に受け止める必要が出てきたと思います。
モノと公共性
齋藤先生:
3点目が、モノという視点です。『パブリック・シングス(Public Things)』というこの本がまさに関わってきます。『公共性』では、公共的な主体や情報交換・意見交換のネットワークという話を書きましたが、ここで挙げたいのは主体の方ではなく客体、対象、モノの方です。例えば、かつての宮下公園のようにデモが出発したり戻って来る場所や、河川敷はパブリック・シングスです。パブリック・シングスはプラスのものだけではなく、むしろマイナスのものもあります。除染土を詰めた黒い袋及びその置き場もいわばパブリック・シングスですし、原発や米軍基地もそうです。パブリックだからいいということには必ずしもなりません。
齋藤先生:
ただ、そういうモノがあってはじめて私たちが出会うということがあります。公園や図書館、河川敷、カフェや街路などは、新しい関係の構築や、これまでの関係の維持・復元を可能にします。そのような機能をモノが持っているという議論を強調しているのがこの本です。主体の側からではなく、実際のシーン、すなわちモノがどうなっているかというところから公共的空間を捉え直す必要があるのではないかと思います。もう一点、公共的なモノというのは、人と人とをひとまとめにするという意味で結びつけるのではなく、それぞれの距離を保ちながら結びつけていきます。これは空間的にもそうですし、時間的にも同じことが言えます。例えば、図書館や公園もそうですし、これまでに建てられてきた建物や公衆電話もそうです。これらは人と人の「あいだ」です。公衆電話はかなり減少してきていますが、アメリカでハリケーンがあった後携帯電話が使用不可能になった際に、非常に貴重なコミュニケーション手段として蘇ったことがあります。普通は打ち捨てられているような公衆電話は、災害を生き延びて劇的な状況においてその役割を復活させたわけです。
このようにモノのあり方が、人々を結びつけたり切り離したりする機能を果たしていることを『公共性』の中でもっと書ければよかったなと思います。もっとも、これは本の出版後に考えたことですから、その点が大事だと思うようになったのが大きな変化です。
『公共性』本でも引いたアーレントの『人間の条件』に、「世界」という概念が出てきます。世界はモノから成り立っています。建築物などのハードなものもあれば、音楽作品や本などのソフトなものもあります。アーレントは、世界を構成しているモノや作品について強調していて、それが丁度人々の「あいだ」にあって介在していくとしています。楽曲や演劇的なパフォーマンスは「あいだ」を構成し、実際にそれを見た人が様々に解釈します。同じ事柄であっても、人によって見方やアプローチの仕方、使い方は異なるわけです。これは時間的にも同じことがいえます。先に憲法の話をしましたが、法も一つの作品であって、それを今どう解釈するかは過去とは異なるかもしれません。このように、具体的な形をとっているかどうかは別として、モノや「あいだ」という概念を使って、アーレントは世界に対する見方を示していました。具体的なモノを扱う建築や都市計画のみなさんにも、この点は関係するのではないでしょうか。
—–インタビュー前編ここまで—–
インタビューの続きが気になるという方も多いと思いますが、前編はここまでです。命名権や時間貸しなどにより、パブリックスペースへの市民のアクセスを限定的なものにしかねないというお話は、民間事業者によるパブリックスペースの管理運営や公共サービスの提供が増えてきたいま、注意して考えなければいけないように思いました。この点については、インタビュー後編で、泉山編集長による昨今のパブリックスペース活用事情の解説を交えてお話がありますので、お楽しみに。
『公共性』執筆後、齋藤先生が新たに考えた3点はどれも示唆に富んだ内容でした。1点目の公共性における時間軸の観点、すなわち「現在を中心とし、我々だけの意思で世界の在り方、公共的なもののあり方を決めない」ということは、東日本大震災後私たちが強く感じていることではないでしょうか。
2点目の「経済的な格差が、空間的に翻訳されていく」ことで「自分とは違った場所(階層)に生きている人への関心が薄れてくる」というご指摘は、アメリカほど顕著な事例はなくとも日本でも少しずつ広がりつつあるのかもしれません。民間事業者によるパブリックスペースの活用が、その空間の利用者を限定していくということも、この二点目を助長する可能性を持っていると思いました。
3点目は「モノのあり方が、人々を結びつけたり切り離したりする機能を果たしている」という観点でした。インタビュー前編にかかる部分だけでは、モノと空間及び公共性の関係についてはまだ十分明確にはなっていないかもしれませんが、インタビュー後編の中でより具体的な形で明らかになりますので、乞うご期待です。
All photos by Ayako Honzawa

- この記事を書いた人 本澤 絢子
- 東京工業大学大学院社会理工学研究科社会工学専攻在学中。東京生まれ東京育ちの一人っ子。昨年7月から1年間、交換留学生としてオーストラリア・メルボルンにあるメルボルン大学のMelbourne School of Designに留学中。「誰にとっても必要な”食べること”は、様々な背景を持つ人たちの共通言語になり、社会課題を解決する一助になる」という信念を持ち、コミュニティガーデンやファーマーズマーケットなど、人とパブリックスペースと食と幸せが交わる場所を研究中。今日もそんな場所を求めて、メルボルンを駆け回っています!